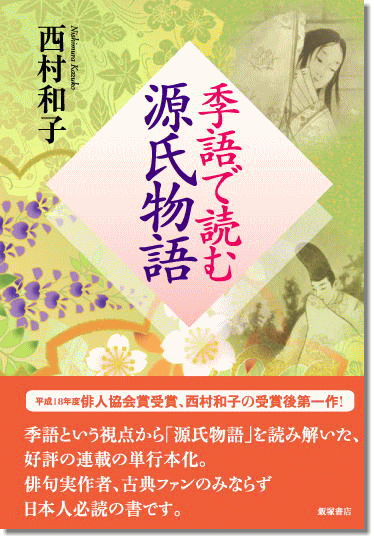 |
―光源氏と織りなす四季曼陀羅―
源氏物語の細やかな季節描写はのちの俳諧の季題、現代の俳句の季語の源ともいえます。
本書は、季語という視点から源氏物語を読み解き、類書のない画期的内容は、俳句実作者・
古典ファンのみならず日本人必読の一冊となりました。
四六判並製 224頁 定価:本体1800円
ISBN978-4-7522-2051-0
|
内容の一部
初音─六条院の新春
時は千年の昔、ところは京の都六条で、光源氏は三十六歳の新春を迎えた。広大な敷地を春夏秋冬の四つの庭に分かち、それぞれの御殿に思い人を住まわせるという贅の限りを尽した六条院は、前年の秋に新築なったばかりである。
人々は賑やかに歯固めの祝いをして、餅鏡(もちいかがみ)を取り寄せて千年(ちとせ)の長寿を願っている。「齢(よわい)」という字が示すように、歯を固めることは年齢を確かなものにすることにつながる。餅鏡は現代の鏡餅のことで、心の臓をかたどったものとも言われる。このあたりまでは千年昔の人々の正月も、私たちと何ら異なるところはない。
だが光源氏の元日は多忙だった。賀客が帰った夕方になって、改めて衣裳を引き繕い、お化粧をして、六条院に住む女性たちのもとを一人一人訪れたのである。それは一見、年賀の挨拶まわりのようだが、源氏の訪れは、人々に幸福をもたらすものだから、神が人間に祝福を授ける姿に限りなく似ている。
紫の上が明石の姫君を育てている春の御殿では、女の童たちが庭の築山の小松を引いて遊んでいる。今日はちょうど子の日で、冬も緑を失わぬ松の根の長さにあやかって長寿を祝おうというのだ。そこに姫君の産みの親、明石の君から歌が届いた。
とし月をまつにひかれて経る人に今日うぐひすの初音きかせよ
今年八歳になる姫君と引き離されたまま、明石は同じ敷地内に住んでいながら、久しく我が子の顔を見ていない。せめて声だけでも聞かせてよという母の思いに触れて、源氏は正月早々、縁起でもなく涙がこぼれそうになる。
その明石の君が住む冬の御殿を訪れたのは、元日も暮れ方になる頃だった。意匠をこらした火桶に香をくゆらした室内には、舶来の敷物に琴が置かれてあるばかりで、源氏を待ち兼ねているはずの女の姿は見えない。硯の周りに取り散らしてある反故を手に取ってみると、淋しい心のうちが書きさしてある。玉と輝く御殿で、一番淋しい正月を過ごす女がここにいる。やがて慎み深く現れた明石の心憎い登場にほだされて、源氏は年の初めの夜を彼女と共に過ごしてしまう。
汀の氷─ひき離された母娘
元日の夜に源氏の愛を射止めた明石の君は、六条院で最も幸せな女性のように見えるが、実は最も辛い体験をして淋しく過ごしていたのである。
明石の君はその名の通り、源氏の須磨流離の時期に、明石で契った女性である。その後、源氏の子を産んだことで都に呼び寄せられたものの、身分の違いから大っぴらに名乗って出ることはできなかった。大井川のほとりの邸で娘を育てつつ、源氏のたまの訪れを待つといった陰の存在だった。
しかし、源氏にしてみれば、たった一人の娘をいつまでもそんな扱いにしておくわけにはゆかない。三歳になったのを機に、紫の上を義母として、袴着(はかまぎ)という幼児の成長を祝う儀式を盛大に行って、世間におひろめをする心づもりだった。
可愛い盛りの我が子を手放すのは辛い。しかしいつまでも自分の手元に置いていては、せっかく源氏の姫君として生まれた幸福を奪うことになる。明石の心は千々に乱れた。
別れの日は「雪かき暗し降り積るあした」にやって来た。白い衣を重ね着した明石は、来し方行く末のことを残らず思い続けながら、汀の氷などを眺めている。みずからの運命の厳しさに耐えているかのような真冬の後ろ姿は、はたで見る人々の心をも打つ。
この子がいなくなったら、こんな寒い日はどんなに心細く淋しいだろうと、涙にくれながら乳母と別れの歌を交す。どんなに雪が深くとも、かならず手紙でこの子の様子を知らせてね、と。そこへ源氏がやって来る。何も知らない姫君は、車に乗るまで抱いてくれた母の袖を引いて、「お乗りなさいな」と、片言ながら愛らしく言う。はげしく泣く明石を慰めつつも、源氏はそのまま姫君を連れ去ったのである。
この雪の日の別れは、幼な児のぬくもりを四六時中肌に感じていた母親が、いきなり我が子をもぎとられる酷さを物語っていよう。心情的な辛さは言うまでもないが、それに加えて母親が体で感じる悲しみといったものが、ひしひしと伝わって来る。
明石の君はそれ以来我が子と会えないまま、六条院の冬の御殿に、ひっそりと移り住んだのである。
【目次より】
初音―六条院の新春 花紅葉―初恋の人 雪明かり―凍る思い
汀の氷―引き離された母娘 毛皮―末摘花は石長姫 紅梅―知る人ぞ知る
垂氷―雪の中の逢瀬 若菜―緑の生命力 沫雪―閉め出された源氏
深山の桜―走り出てきた美少女 花の宴―華やぎと翳りと
朧月夜―世の中のあやまちは 藤の花―宴で目立つ秘訣
霞―源氏の旅立と芭蕉の旅立 春の闇―夜居の僧の告白
四季の庭―自然のあるがままの姿 胡蝶―我が世の春
猫の恋―悲劇のはじまり 形見の花―まろが桜は咲きにけり 他
|
|